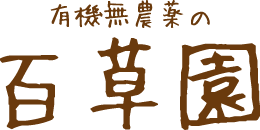-
百姓百品の便り
とうもろこし、イノシシ、狸との競争
トウモロコシを植えたのは10年ぶりくらいになります。柔らかくて甘いスイートコーンはカメムシの害がひどいのでやめていました。今年久しぶりに植えてみたのですが、10年前とは違うトラブルが出ています。イノシシによる食害です。狸にやられることは昔からよくあったのですが、狸の害はそんなには拡がらないので、食べられた分は「しょうがないナ」くらいですんでいました。しかし、10年前にはいなかったイノシシとなると、荒らし方の勢いが全然違います.バリバリなぎ倒して、実の部分をかじり散らして行くのです。
これから熟れるほどに被害はましていくことになるので、まだ少し早いですが、イノシシにやられてしまう前に、出し始めることにしました。まさかこの地域でこんな日が来るとは考えてもいませんでした。
うちのメンバーの福田亜矢子さんはこれまでに2回も、うちの近所で道を移動するイノシシの雄や親子に出会っています。配達メンバーの内田君はに田んぼの代掻きをしていたら、そこに中くらいの大きさのが2頭出てきて、虫を狙ってか田んぼをほじくりはじめたそうです。驚いたことにトラクターで耕しているのに、逃げもしないですぐ脇の田んぼで居続けたそうです。そこまで人間になれているというのも驚きです。かぼちゃをかじられた研修生OBはソーラー電源の電柵を張りました。
イノシシと言えばサツマイモが何よりも大好物、去年7月全滅の被害にあいました。
なので、今年は雨が明ける頃にはアイガモ用の電柵を張って防御策を講じます。
イノシシ外をのがれた貴重なトウモロコシ。しっかり味わってください。
来週も出せることを祈ってます。イノシシとの闘い。人ごとのように書いていいですか。
正直、どうしようもないじゃん。
数年前までは、狩猟が解禁になるとキジなどを狙って、猟犬を離して迷惑だった猟師さん達、なんで最近はこないの??キジではなく、イノシシ狙ってよ。イノシシは、近くにの豚屋さんのメス豚を狙ってくるという噂が。つまり、猪豚(いのぶた)を産まさせるために。。。猪豚(いのぶた)を孕んだメス豚は、もう絶対に豚のオスをうけいれないとか。メス豚の本音の気持ちは、怖くて聞きたくない。
なんでそこまでするん(怒)。少しだったら分けてあげるけど、イノシシは作物を全滅させるから、猟師さんにおお願いするしかない!猪豚(いのぶた)は美味しいそうなので、それは食べたい!
-
百姓百品の便り
自分たちで栽培した有機無農薬の飼料米をやっている卵
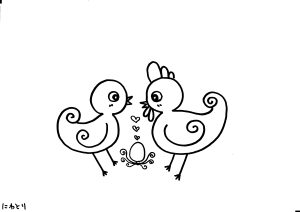
最近、私たちの卵の黄身の色が薄くなったと感じていませんか?
餌の高騰が畜産農家を苦しめていると、新聞などで読まれたことがあると思います。実は、私たちも苦しんでいる一人です。
鶏にはトウモロコシをやることが多いのですが、百草園では、特別に輸入された「遺伝子組み換えではないトウモロコシ」をやっています。この「遺伝子組み換えではないトウモロコシ」は、それでなくても普通の輸入トウモロコシより高いのですが、昨今の「働き方改革」の影響をうけ、とてもコストが高くなっていると飼料会社の人が説明にきました。
トウモロコシは岡山に荷下ろしされ、それからトラック便で九州まで配達されます。これまでは、関東までのトラック便の帰りの空トラックに乗せてもらうという自助努力で運賃を安くするようしていたそうです。しかし、「トラック運転手のそのような休みのない働き方はいけない」ということになり、一泊いれないと運べなくなったそうです。それで輸送賃が高くなるということでした。
請求書をみると「遺伝子組み換えではないトウモロコシ」が、一昨年より2倍以上の価格になってきているので、私たちは自己防衛としてその量を減らしました。そして、自分たちで栽培した「飼料用のお米」の量を増やしています。無農薬の有機栽培ですから、輸入の「遺伝子組み換えではないトウモロコシ」よりずっといいものです。
ただ欠点は、卵の黄身の色がエサに影響を受けるということです。エサに黄色系のパプリカやマリーゴールドなどを混ぜると黄身の色が濃くなります、トウモロコシの代わりに米を食べさせると黄身の色は薄くなります。卵の黄身が、薄い黄色でも濃い黄色でも赤い色でも、黄身の色と鮮度や栄養価は一切関係ありません。ですから、今までどおり安心して食べてください。
※遺伝子組換え技術が開発され、除草剤耐性作物、害虫抵抗性作物、耐病性作物などの作物が、多くの国々で栽培されています。トウモロコシには特に、グリホサートという除草剤耐性のものが大量に栽培されていますので、普通に輸入トウモロコシをつかえば、ほぼ間違いなく遺伝子組み換えのトウモロコシです。もちろん、除草剤グリホサートが使われています。それを避けたくて、百草園のニワトリには「遺伝子組み換えではないトウモロコシ」をやっています。 -
百姓百品の便り
さー、お米作りがはじまります
 #
#
いよいよ農繁期です。昨日は、お米の苗を育てる育苗箱に、土をいれタネをまきました。お米5反分と飼料米9反分です。写真では機械の前で余裕でピースマークをしていますが、朝9時から夕方6時までの強い日差しの中でのお仕事、最後はくたくただったはず。ご苦労さんでした。
私も人手がたりないと狩り出され、座ったままできる仕事をして、猫の手よりちょっとましだったと思いたい。飼料米は、鶏さんたちにあげる餌として栽培しています。有機肥料・無農薬の国産のお米を食べている鶏さんは、日本ひろしと言えど、そんなにないですよ。
今年も豊作でありますように!!
お米作りって幸福感が強いです。
だって、秋には黄金の稲穂が垂れるんですよ。 -
百姓百品の便り
やめられない不器用さが、いつか世界を変える
今月は、年に1回の会費を200円徴収します。
どんなことにこの会費を使ってきたか、新しく百草園の消費者になってくれた人もいますので、すこし説明しますね。農業を経営でみると、儲かる産業とはいえず、時々萎えます。
それでも40年間有機農業を続けてきたのは、消費者との提携という農業の新しい仕組みに夢を感じたからです。
他の産業では、売る方が価格を決めることが前提です。でも農業では農家はつくるだけで価格を自分でつけることすらできない仕組みでした。
そうではない、売り買いだけではない仕組み「食卓とそれを囲む人が見える生産者」と、「畑や四季、それをつくるお百姓さんが見える消費者」がともにつくっていく関係をめざして百草園は出発しました。百草園と共に歩む消費者の会(千草会)もでき、一緒に、野草摘みと野草料理の会をやったり、田植えをやったり、芋掘りをやったり、いろいろやってきました。国際映画祭も準備しました。(コロナで開催できませんでしたが)
会費は、消費者と生産者が、そんな関係をつくっていくための費用と思っています。福島原発が爆発したときは、私は福島の武藤類子さんに会いに行き、お話を伺って、福島原発から30k圏内の三春町に住み続ける武藤さんとその友人に野菜を届けはじめました。今もそれは続いています。
そのために、千草会の有志が、武藤さんに野菜を送る費用を毎月200円寄付してくれています。福島であれだけの経験をしたのだから、「地震大国の日本では原発はいらない」という方向に動くのではないかという希望も抱いたのですが、実際はどの原発も再稼働が始まってしまいました。とても悔しいです。
東電の責任を追求する裁判を続ける武藤類子さんの言葉を紹介します。
「若い人たちも行動を起こしてくれている。数ある原発訴訟の中でも小さな勝利があったりする。がっかりすることも多いけれど、少しずつでも、やはり人は進化していくと思うんです。変わるのは時間がかかる。小さい努力を積み重ねながら、諦めず、地道に訴えていくしかないですね。みんなでね」
※武藤類子さんの現在の想いの全文は「福島の記録 武藤類子」で検索してください。https://fukushimatestimony.jp/live/8.html
有機農業だって有機農業推進法という形で国が認めるまで40年近くかかったのだから、諦めないで続けること、というか、やめられない不器用さが、いつか世界を変えると思いたい。
-
百姓百品の便り
耳って不思議???
英語の聞く力と話す力をつけたいと、長年あれやこれや、やっています。そんなよくある悪戦苦闘の日々で、最近驚きの気づきが。。。。。
英語が得意なわけではなく、学生のころは辞書というものをを引いたことがなく、単語帳も作ったことがないという私が、ふとしたことがきっかけで英語の勉強をはじめて20年・・・ゆっくりゆっくりと上達しているようです。多分。まったく自信はつきませんが。
それで、聞きとれて、話すことができることが、最近の私の課題なのですが、話す相手いないからかとても難しい。なんて言い訳で、間違いを恐れて話が続かない。
せめて聞く力だけでもつけたいと、英語のドラマを見続けることにしました。朝ご飯を食べながら、昼食を食べながら、夕ご飯の時も、休憩の時も、日本語の字幕つきの画面を見ながら、英語を聴き続けました。初めは会話が音としてしか聞こえなかったのですが、ところがある日「あれ、聞き取れる」って言う感じになったのです。「言っていることがわかるじゃん」って。
英語は、突然聞き取れるようになるっていいますけど、ほんと、そんな感じです。
他のドラマに変えると、俳優も変わるので、その発音になれるまでまた聞き取れないのですが、頭が飽和状態になったときかな??聞き取れるようになるんですよ。
会話型AIに情報を入れ続けると、その情報がAIの中で繋がって、紋切り型の会話ではない、人間の感情に似た話をできるようになる時が来るっていいますが、そんな感じです。
耳ってすごく不思議で、すごい能力を秘めているみたいです。
英語はまだ上手ではないです。でも、そのうち、外国に行かなくても、話せるようになるんではないかと、希望が持てた体験でしたから、言いたくってしかたない。。。。。
-
百姓百品の便り
ローカルフェアトレードがいよいよ動き出すかも
フェアトレードは学校の授業でも扱われていますから、熊本でもかなり浸透してきました。では、ローカルフェアトレードとは何でしょう?
選ばれる熊本を目指して
私たちには見えていませんが、現在すでに、外国の人々は日本の経済・社会の重要な構成員となっていて、県内でも多くの外国の人々が働いています。でも、全国では5 年間で約 35 万人を受け入れる予定の特定技能の外国人も、所得水準の高い大都市圏へ流出するのではないかと言われている中で、熊本県は「選ばれる熊本(地方)」てをめざして、行政サービスの対応及びコミュニティにおける多文化共生を模索し始めているのだそうです。県内のエスニック料理と外国人が多数働く農業をつなごう
その多文化共生の一つに、学園大の申明直先生が提唱されているローカルフェアトレードの考え方がぴったりなんです。多くの外国人が働く農業生産現場と、消費をつなぐことで、多文化共生を実現するというものです。もちろん、フェアトレードというからには経済の仕組みは必須です。まずはその第一段階として、県内のエスニック料理店を学生と一緒に調べたそうです。
現段階では、インド料理や中国料理、韓国料理がそれぞれ約30店舗。ベトナム、スリランカなども10店舗近くあることがわかっているとか。それをネット上だけで調べるのではなく、出向いて行くので、「どれだけエスニック料理を食べたことか」という先生の表情は楽しそうでした。
一方で、JICA(国際協力機構)による2022年の調査によれば、農業生産現場で働く外国人の割合は2割を超えているというデータがありますが、私たちには見えていませんよね。ローカルフェアトレードの一歩として、まずはこれをネットでつないでいきたいと申先生は考えています。つまり、エスニック料理店の紹介ページとローカルフェアトレードに理解ある生産者の紹介のページをつくり、それが販売でつながっていくようなものにしたいということでした。
そこに百草園も入ってほしいと言われたので、即OKの返事を。多文化共生の基準と持続可能な環境基準も必要
今後1年間議論を重ねて、ローカルフェアトレードの基準(多文化共生の基準と持続可能な環境基準)を決めていきたいし、その基準を満たした場合の認証マークも決めていけたらという先生の話は魅力的です。
私は食べることが好きなので、エスニック料理店の紹介はワクワクします。そしてそこで文化や人と農業が出会えれば、それはきっと楽しい未来になるでしょう。
百草園の場合
百草園にはナイジェリア出身のオビロさんがもう長く勤めています。
ベトナム出身のリンさんとも、3年も一緒に働きました。
そして、多文化共生について語りつくせいほどのことを二人から学びました。私が多文化共生という考え方にであったのは、20年ほど前にサンフランシスコにNPOの研修で行った時です。サンフランシスコではそのことをメルテングポット(人種のるつぼ)と表現していました。
-
百姓百品の便り
謹賀新年2024

新年早々、大きな災害のニュースが飛び込んできました。熊本地震を体が覚えていて、恐怖がよみがえります。
こんな時にFacebookで新年の挨拶をするのも躊躇われたのですが、74歳を迎える私たちの新しい年への決意でもありますので、アップすることにしました。
お読みください。
百草園
間 司 澄子 -
百姓百品の便り
卵の事情・・・卵の汚れをせっせと落としながら、書きたくなったこと
百草園では平飼いの自然卵養鶏で、産卵箱にワラや籾殻をしいたところに産卵するようなっています。産卵箱は5〜6カ所は用意してあるのですが、鳥たちはある箇所にかたまって何羽も折り重なるようにして産む習性がありますので、破卵したりして、汚れる卵がどうしても出てしまいます。
普通のケージ養鶏では、向きを変えられない狭い空間で、産み落とした卵はそのままケージに沿って転げ出る様になっていますので、汚れも少なく、その上、全個数の洗卵と次亜塩素酸消毒が義務づけられています。
私たちは洗卵すると、卵の表面の防護膜がなくなってしまうのと、次亜塩素酸など使いたくないので、汚れはまず乾いたままふきとるか、ぬれたスポンジでふきとり、それでも落ちないような物は手洗いで流水中で洗っています。 -
百姓百品の便り
輸出企業は消費税の還付金もらってる??
9月分の引き落としの手続きをすることを、インボイス対応の請求書の作成に夢中になっていたら、忘れていました。本来の引き落とし日である15日の日曜日に突如、「もしや引き落としの手続きをしていないかも」と頭がまわりだし、パソコンの前に走って調べたら、やっぱりやっていなかった。
最近、事務のボカミスが目立って、嫌になります。「インボイス対応の請求書、かんぺきにつくったぜ」と達成感もりもりだったのですが、今は落ち込んでいます。「事務量を増やす、インボイスめ!!」です。
インボイスは、小さな事業者からも消費税をとるためということのようですが、
日本の大手企業を中心に構成された経団連(日本経済団体連合会)と国は、消費税を推奨し「もっと消費税率を上げれば良い」と考えているという記事を目にしました。その理由の一つに、輸出をする企業は還付金をもらえるからだそうです。
・1位 トヨタ自動車:還付金額 6003 億円
・2位 本田技研工業:還付金額 1795 億円
・3位 日産自動車:還付金額 1518 億円
・4位 マツダ:還付金額1042 億円
・5位 デンソー:還付金額 918 億円
私はお金にうといのでよく分かりませんが、確かトヨタは海外に子会社を作るという方法で、国内の法人税も払っていませんでしたよね。法人税を納めないだけでなく、私たちからあつめた消費税をつかって還付金をうけていた???つまり、国内分を含め、消費税もまったく払っていないということでしょう。
これって、どういうこと???
だれか、税金に詳しい人に教えて欲しい!! -
百姓百品の便り
ニホンミツバチのハチミツが採れました

ニホンミツバチが我が家の木の壁に毎年巣をつくって10年以上。壁に巣を作っても蜜がとれないので、つまらないと、箱型の巣箱をおきました。毎年分峰した集団がやってきて箱にははいるのですが、スズメバチが襲撃したり、すむしにやられたりして、最後は蜂がいなくなってしまって、蜜がとれなかったのですが、とうとう今年、蜜がとれました。それも瓶に2本も。
嬉しいですね。どうやって食べよう!!!
残った巣屑といわれるものも、蜜蝋とか色々つかえるとはいわれているけど、まだどうしていいか分からず、そこらへんにポイしてある。
一歩づつ一歩づつ。