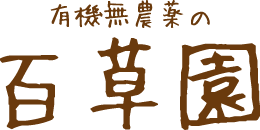-
白米
大根の押し寿司
 百草園と万菜村の1品持ちより新年会で美味しかった大根寿司。
百草園と万菜村の1品持ちより新年会で美味しかった大根寿司。
すぐに作ってみました。
大根とおぼろ昆布が旨味をだしてくれて、とても美味しいです。
押し寿司器をもっていないので、タッパーに入れて作りました。だから、すこし不細工。押し寿司器を使った時のように角がたっていませんが、それでも美味しそうでしょう。<材料>
① 白米(今日は黒米入りを使っています)1合
② 梅干し 1個
③ 大根
④ ラディッシュ
⑤ 米酢
⑥ 塩少々
⑦ おぼろ昆布<作り方>
① 白米は普通の炊いておきます。固めの方がいいです。
② ①に梅干しの果肉をたたいたものを混ぜます。
③ 大根とラディシュを薄く輪切りにして、薄く塩をしておき、しんなりすすまで置きます。
④ ③を絞って、米酢につけ、酢が染みるまで待ちます。この時、大根とラディッシュは別々にしないと、大根にラディッシュの色がつきます。
⑤ 押し寿司器(私はタッパー)にラップを大きめにかけ、ラディッシュ、大根の順で並べます。
⑥ おぼろ昆布をたっぷり目に敷いて、その上から冷めた寿司ご飯を入れます。
⑦ 隅の方まで気を使って手でしっかり押さえ、その上から、一回り小さいタッパーで押します。
⑧ ひっくり返して、包丁で切ってできあがり。私は押しが足りませんでしたが、それはそれで美味しかった!!!
(さらに…) -
白米
鶏肉炊き込みタイ料理
 百草園の鶏肉は、卵を産んだ後なので固いのですが、運動をさせず、短期間(1ヶ月半程度)で成長させるブロイラーの肉と較べて、味はバツグンです。
百草園の鶏肉は、卵を産んだ後なので固いのですが、運動をさせず、短期間(1ヶ月半程度)で成長させるブロイラーの肉と較べて、味はバツグンです。
私たち以外で、この肉を食べことができる人はいないだろうと思っていたのですが、タイで暮らしたことのある私の英語の先生が、「百草園の鶏肉をタイ風に味付けをして食べると、ブロイラーの肉は食べられなくなる」と大絶賛。私も作り方を習って作ってみたのですが、簡単なのに、美味しい!!
やっぱり固いですが、美味しいので気になりません。写真は盛りつけが乱れています。鶏肉を切って炊飯器に入れたせいです。ブロックのままいれて、盛りつけの時に切れば、美しく見えるようです。
レシピを紹介しますね。
<材料>
=ご飯=
・白米 2合
・にんにく 1かけ
・しょうが 1かけ
・ナンプラー 小さじ1
・塩 胡椒 適当
・百草園の鶏肉 半匹分(今回はもも、胸を使いました)
=タレ=
・ナンプラー 大さじ5
・砂糖 大さじ1(できれば、白砂糖ではない方が良い)
・青とんがらし 適当
・赤とんがらし 適当
・ライム(ユズやレモンでもいいし、なければ酢でもいい)1個
=つけわせ=
・キューリ 1本
・ネギ
・アーモンドかピーナツ<作り方>
①炊飯器に米2合と、にんにく、生姜をすりおろしたもの、ナンプラー 塩、コショウを入れ、普通に炊く時の量の水をいれ、鶏肉を上に乗せ、普通に炊く。
②タレの材料を全部をタッパーに入れ、冷ましておく。
③ご飯が炊きあがったら、ご飯と鶏肉を盛りつけ、キュリを飾り、タレをかけ、細く切った白ネギとピーナツをみじん切りにしたものを、トッピングする。とても簡単です。
タレは作り置きしておいて、他の料理でも使えると先生は言っていました。
(さらに…) -
白米
栗ごはん 黄色くならなかった
 栗をむくのって大変!
栗をむくのって大変!
研修生と一緒に食べるお昼ご飯のために、8合の栗ごはんを作ったのですが、レシピどおりにすれば、800gの栗を剥かないといけません。800gの栗って、大きなザルに大盛りの量です。あまりの大変さに、「栗は1人1個はいれば良いのではないかしら。」なんてブツブツ。
栗を1時間ほど水につけておくのが栗をむきやすくするコツだと聞いて、それをやったのですが、渋皮が手強くて、さほど早くはなりませんでした。
もし栗のむき方と、保存の仕方をご存知の方は教えてください。ところで、8合の栗ごはん、何人の為のお昼ご飯だと思いますか?。。。。。。5人です!
若い人の食べっぷりって気持ち良いほどスゴいです。<材料>
生栗 400g
もち米 2合
白米 2合
みりん 大2
醤油 大2
塩 小2
昆布 適量<作り方>
①生栗はぬるま湯につけて30分おく。
②皮と渋皮を包丁で丁寧に削ぎとり、水で洗って汚れを落とす。
③餅米とお米を洗って、みりん、醤油、塩を入れ、水を加えて4合の目盛りに合わせ、それから栗と昆布を入れて炊飯器で炊く。
④でき上がったら、昆布を取り出す。
栗を黄色くホクホクするための工夫が書いているのを見つけて、やってみたのですが、黄色くなりませんでした。栗の品種も関係あるのかもしれませんが、良い方法があれば、これも教えてください。
ということで、味付けに醤油を使っている事もあって、真っ白いご飯に、黄色のホクホク栗なんて色にはなりませんでしたが、味は、昆布出汁のでいか、とても美味しい栗ごはんになりました。昆布を取り出した後は、煮付けにしましょう。
(さらに…)