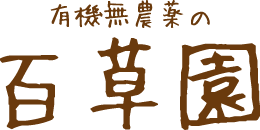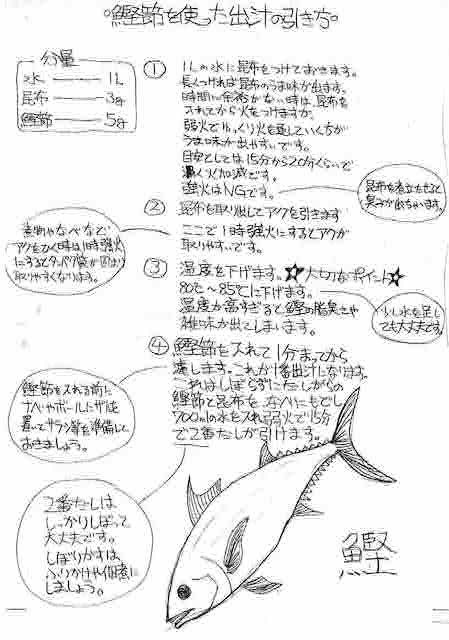-
昆布
かつぶしと昆布でつくった出汁と百草園のうどん
11月8日に「くまもとのタネと食を守る会」主催で行われたワークショップに参加しました。良い出会いもあって,楽しかった!
今日は、お土産にいただいた鰹節と昆布を使った出汁(だし)に、百草園の細麺のうどんを入れて、お昼ご飯をいただきました。
出汁も本物でかつ節や昆布の味を感じることができて、うどんも小麦の味がよくて、美味しくてお腹いっぱい。
つくったのは,人参の天ぷらのトッピングとタマネギとお肉の甘辛煮のトッピングのうどんです。ゴボウがあったら、ゴボウの天ぷらをつくりたかったのだけれど、畑から掘ってなかったのでつくれませんでした。残念〜。百草園の麺は、自分達の畑で麦を栽培して、栃木県の黒澤製麺所まで小麦を送って麺にしています。
黒澤製麺所は無農薬で、有機栽培の小麦しか扱わないという、日本で数少ない、こだわりの製麺所です。
製粉にもこだわり、小麦の約8割を製粉することで、色は黒っぽく小麦の香り豊かなうどんが仕上がります。
代表の黒澤真治さんは、栃木に住む知人を通じて、「廃業する製麺所が機械の後継者を探している」と知り、機械を譲り受けて開業するために埼玉県から栃木へ移住された方です。良い製麺所に出会いました。
(さらに…) -
 昆布
昆布
たけのこ料理
タケノコの季節ですね。
今日はとてもよくアクがぬけたので、天ぷらとタケノコの炊き込みご飯にしました。
※写真は天ぷらとタケノコの炊き込み御飯です。タケノコご飯の作り方を紹介します。
<材料>
① タケノコ
② こんぶ
③ あげ
④ 人参
⑤ しょうゆ
⑥ 塩
⑦ 酒
⑧ 砂糖 少々
⑨ タケノコのアク抜きにヌカ<作り方>
① タケノコは皮をつけたままヌカをいれて1時間から2時間ゆでて、湯で汁のつけたまま冷ましておきます。
② アクのぬけたタケノコ、人参、あげをざっくり切っておきます
③ 厚手の鍋で②を炒め、砂糖、醤油、塩、酒で濃めに味付けしておきます。
④ お米を昆布をいれて、③をいれ炊きます。
⑤ 炊きあがってから、塩で味を調整します。昆布出汁が効いて、美味しい炊き込み御飯ができあがり。
(さらに…) -
昆布
あげと揚げなすのおひたし
 この季節のなすは、なすの木が夏の残り火の用に最後の力を振り絞ってつけた実なので、少し皮が硬いです。皮を少し剥いて料理しましょう。
この季節のなすは、なすの木が夏の残り火の用に最後の力を振り絞ってつけた実なので、少し皮が硬いです。皮を少し剥いて料理しましょう。<材料>
①あげ 小さめ2枚
②なす 小さめ2本
③油 適量
▼出汁
④こぶ
⑤醤油
⑥出汁
⑦あればショウガを擦ったもの<作り方>
① なすの皮を虎むきにし、3〜4センチの輪切りにしておく
② なすを170度の油(箸を入れた時に泡がすぐでる)で揚げ、出汁汁に浸します。
③ あげは空いりし、軽く焦げ目がついたら出汁に浸します。ナスを油は合いますね。
(さらに…) -
昆布
タケノコとひろうす(がんも)の煮物
 タケノコの季節です。千草会の皆様には堀たてのタケノコをヌカをつけてセットにいれています。
タケノコの季節です。千草会の皆様には堀たてのタケノコをヌカをつけてセットにいれています。
ヌカでアクをぬいて、料理に使ってください。
今日はアク抜きは省略して、ひろうすとの煮物の紹介します。
料理がシンプルな時は、だしが味の決めてかな。今日は昆布と,カツオブシのだしの素を使いました。<材料>
① アク抜きの済んだタケノコ
② ひろうす(がんも)
③ 昆布
④ 砂糖
⑤ 醤油
⑥ 酒
⑦ カツオブシのだしの素<レシピ>
① タケノコを一口大にきっておく。
② 鍋に水をいれ、昆布とカツオブシのだしの素をいれて一煮立ちさせる。
③ タケノコとひろうすをいれ、砂糖、醤油、酒をいれて味を整え、煮込む。
④ 時々弱火にして、味をしみ込ませ、煮汁が1/3程度になるまで煮込んで終了。
(さらに…) -
昆布
カブとラディッシュのサラダ
 カブは葉っぱ丸ごと甘酢漬けにしますが、それに飽きた時、サラダに変身させましょう。ラディッシュも彩りにいれると美味しそうです。
カブは葉っぱ丸ごと甘酢漬けにしますが、それに飽きた時、サラダに変身させましょう。ラディッシュも彩りにいれると美味しそうです。<材料>
① カブ 2個
② ラディッシュ(甘酢漬けをしたもの) 3個
③ 昆布 少々
④ 砂糖 小さじ1
⑤ 酢 大さじ2
⑥ オリーブオイル 少々
⑦ クリームチーズ 適量<作り方>
① カブは洗って、皮のまま薄切りにし、茎と葉もザックリ切っておく。
② ①に塩少々をふって20分ほどおく。
③ しんなりとしたら、手で絞り、水気を切る。
④ 昆布は、絞ったぬれぶきんで表面を拭き、キチンばさみで細く切る。
⑤ ③④に砂糖と酢をいれ、混ぜて味をなじませる。
⑥ ラディッシュの甘酢漬けをスライスし加える。
⑦ ⑥を皿に盛る時に、オリーブオイルをかけまわし、クリームチーズをトピングする。クリームチチーズは写真より多良い方が美味しいようです。
(さらに…) -
昆布
豆ご飯&グリーンピースと真竹煮物

 やっと、グリーンピースの季節がやってきました。露地栽培だと旬の時期は短いのです。今しか作れないメニューなので、頑張って作りました。
やっと、グリーンピースの季節がやってきました。露地栽培だと旬の時期は短いのです。今しか作れないメニューなので、頑張って作りました。
豆ご飯とグリーンピースと真竹煮物です。
真竹もこの季節だけのものです。一般的に食べられている孟宗竹に較べると細くてスラットした形をしています。アクを抜く必要がないし、孟宗竹のように長時間煮なくても良いので、私は孟宗竹より好きです。なんで一般に流通しないんでしょうね??豆ご飯
<材料>
① グリーンピース
② 昆布
③ 塩
④ お米<作り方>
① お米を研いでおく
② お米の量の水と,昆布と塩、グリーンピースを炊飯器にいれて炊く。
豆は後で混ぜるより、はじめから炊き込む方がご飯となじんで美味しく仕上がります。
これだけなのですが、うっすらとした塩味で何杯もおかわりしたくなる味です。塩味が足りないときは炊きあがってから、足してください。グリーンピースと真竹煮物
<材料>
① 真竹
② グリーンピース
③ アゲ
④ 醤油
⑤ みりん
⑥ あごだし<作り方>
① 真竹は皮に切り目を入れ剥きます。簡単です。
② そのまま5ミリ幅で斜め切りします。
③ アゲは適当な大きさに切っておく。
④ グリーンピースは剥いておきます。
⑤ ①〜④の材料に水と出汁をいれて、沸騰したら醤油、みりんで味つけをし、煮込みます。
(さらに…) -
昆布
ワラビご飯
 年に1度くらいしかつくらないワラビ料理。
年に1度くらいしかつくらないワラビ料理。
今日は、アゲと一緒に炊き込み御飯にしました。
山菜はどれもですが、アク抜きが大切。
アク抜きが上手にできれば、春の味を楽しめます。<材料>
① ワラビ 200g
② 木灰 30gくらい(灰がないときは重曹でもいい)
③ お米 4合
④ アゲ 小さいの4枚
⑤ 昆布 一枚
⑥ 塩
⑦ 醤油
⑧ みりん<ワラビのアク抜き>
① ワラビの穂先を切ることもありますが今回はそのままにしています。根元は固い所を切り落とす。
② 鍋にお湯をわかし、ワラビと灰を入れ、20秒ゆでる。
③ 火を止めて、ワラビが浮いてこないように落とし蓋をし一晩置く。
④ 朝からアクのでた水を捨て、何度か洗う。
これで、すこし食べてみて、アクが抜けていたらOK。
まだアクが抜けていない場合、さらに水に浸しておいてください。<炊き込み御飯>
① お米4合を洗っておく。
② アク抜きしたワラビを、2センチ程度の長さに切りそろえる。
③ アゲを2センチ程度の長さの細切りにしておく。
④ 炊飯器にお米と昆布、ワラビ、アゲをいれ、塩、醤油、みりんを加えて、さらに水を4合のところに合わせていれ、スイッチをいれる。
⑤ 炊きあがったらご飯を混ぜて味を見、足りないときは塩をたす。炊く前の味はすこし濃いかなと感じるくらいが、炊きあがった時にちょうど良い味になるようです。
(さらに…) -
昆布
金山寺味噌
 金山寺麹を買ってきて、金山寺味噌をつくりました。熊本では「しょんしょん」とか、「しょうゆの実」って言っています。
金山寺麹を買ってきて、金山寺味噌をつくりました。熊本では「しょんしょん」とか、「しょうゆの実」って言っています。
つくるっていっても、買ってきた麹の袋に書いてあるように、醤油とお湯、焼酎、みりん、こんぶ、ショウガを入れるだけなんです。
写真は作ったばかりのものです。10日もすると発酵してまろやかになり、美味しい「しょんしょん」の出来上がり。あとはゆっくりと発酵が続き、さらに美味しくなります。
ご飯と一緒にたべても良いし、生のキャベツをザクザクと切ったものやキュウリにつけても、おかずの一品になります。
忙しい時に便利です。
(さらに…) -
昆布
細切り昆布の常備食
 細切り昆布をたくさんいただいて、野菜もニンジンしかなかっったので、この二つで常備食を作りました。
細切り昆布をたくさんいただいて、野菜もニンジンしかなかっったので、この二つで常備食を作りました。
美味しいくて、常備食にならず食べてしまいます。<材料>
①細切り昆布
②ニンジン
③かつおの粉
④醤油
⑤みりん<レシピ>
①細切り昆布は水で戻しておきます。(戻した後の水はすてないで、味噌汁の出汁として使います)
②ニンジンも細くきっておきます。
③フライパンにゴマ油を熱し、水をきった①と②をいれて炒めます。
④みりんと醤油をフライパンの外側から回し入れ、鰹の粉を入れて、汁気がなくなるまで炒める。
(さらに…) -
昆布
干タケノコのメンマ
 干タケノコを今日はメンマ風に作ってみました。
干タケノコを今日はメンマ風に作ってみました。
これだけで、ご飯がおかわりできそうです。
昆布の水出汁も使っています。<材料>
① 干タケノコ
② 油(ごま油がなかったので、菜種油使ってます)
③ タマネギ
④ しょうゆ
⑤ みりん
⑥ 酢(今回は黒酢を使いました)
⑦ 砂糖(きび砂糖を使いました)
⑧ 昆布の水出汁
⑨ 粗挽唐辛子
⑩ 重曹<作り方>
① 干タケノコを一晩水に浸け。戻しておきます。
② ①を1センチ幅くらいで切り、重曹をいれたお湯で10分ほど煮るとさらに柔らかくなります。
③ タマネギはすりおろし、それに材料の④〜⑧を全部いれて調味料を作っておきます。
④ ②を水洗いしたものを、中華鍋に油をしいていれ炒めます。
⑤ ④に作っておいた③の調味料を回し入れ、焦げないように煮汁がなくなるまで煮ます。
⑥ 最後に、粗挽き唐辛子を入れ出来上がり。
(さらに…)